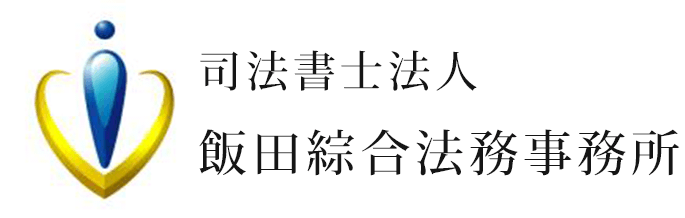- はじめに:相続に関するよくある疑問
相続は、多くの人にとって人生で直面する可能性のある重要な法律問題です 。しかし、そのルールは時に直感に反するように感じられることもあり、特に「誰が相続人になるのか」という点は誤解が生じやすい部分です 。中でも、「自分の甥や姪は相続人になることがあるのに、なぜ自分の叔父や叔母は法定相続人として相続できないのだろうか」という疑問はしばしば耳にされます 。
このような疑問の背景には、一般的な家族観や親族間の情緒的なつながりと、法律が定める相続人の範囲や順位との間にギャップが存在することが考えられます 。法律は、社会の安定と公平性を期すために客観的で明確な基準を設けていますが、それが個々人の感覚と必ずしも一致するとは限りません 。
本稿では、この疑問に答えるため、日本の民法が定める「法定相続人」の制度と、甥や姪が相続人となる場合に適用される「代襲相続」の仕組みを解説します 。この知識は、自身の意思に沿った相続を実現するための遺言作成など、積極的な生前対策の重要性を認識するきっかけともなるでしょう 。
- 相続の基本:法定相続人と相続順位
相続が発生した際、遺言書がない場合や、遺言で財産の分配が指定されていない部分については、民法に定められた「法定相続人」が、定められた順位と割合で遺産を相続します 。
まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります 。ここでいう配偶者とは法律上の婚姻関係にある者を指し、内縁のパートナーは法定相続人に含まれません 。
配偶者以外の法定相続人には、以下の順位が定められています 。
- 第一順位:直系卑属(子や孫など) 被相続人に子がいる場合、その子が第一順位の相続人となります 。もし子が相続開始以前に亡くなっていた場合などには、その子の子、つまり被相続人の孫が代わりに相続人となります(代襲相続) 。
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母など) 第一順位の相続人が一人もいない場合に限り、被相続人の父母が第二順位の相続人となります 。父母が共に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります 。
- 第三順位:兄弟姉妹 第一順位と第二順位の相続人がどちらもいない場合に初めて、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります 。そして、この兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっていた場合などには、その子である甥や姪が代わって相続人となります(代襲相続) 。
法定相続の重要な原則は、先の順位の相続人が一人でもいる場合、後の順位の者は相続人になれないという点です 。
- 甥・姪が相続人となる「代襲相続」とは?
被相続人の甥や姪が相続人となるのは、「代襲相続」という制度によるものです 。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続廃除によって相続権を失っていた場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です 。
甥や姪が代襲相続人となるのは、その親にあたる被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人として相続するはずだったにもかかわらず、相続できない場合に限られます 。
ここで非常に重要な点が二つあります。 一つは、甥や姪の子(被相続人の姪孫や又甥・又姪)による「再代襲相続」は認められないという点です 。兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪の一代限りで終了します 。 もう一つは、兄弟姉妹が「相続放棄」をした場合、その子である甥や姪は代襲相続できないという点です 。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったとみなされ、相続権そのものが消滅するため、子に移る余地がなくなるのです 。
- 叔父・叔母が原則として相続人になれない理由
本題のもう一方である「なぜ叔父・叔母は原則として相続人になれないのか」という点ですが、結論は被相続人の叔父や叔母が、日本の民法が定める法定相続人の範囲に含まれていないからです 。
民法が定める法定相続人となる血族は、被相続人の直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)、そして兄弟姉妹に限定されています 。被相続人から見て、叔父や叔母は「傍系血族」にあたりますが、民法が相続権を認める傍系血族は、被相続人自身の兄弟姉妹とその子(甥・姪)までです 。それより遠い親族である叔父・叔母や、いとこ(叔父・叔母の子)には法定相続権が及びません 。したがって、他に法定相続人となる親族(子、親、兄弟姉妹など)がおらず、身寄りが叔父・叔母しかいないという方の場合、何もしなければ法定相続人が一人もいない「相続人不存在」の状態となり、最終的に財産は国庫に帰属することになってしまいます。こうしたルールがあるからこそ、「お世話になった叔父さん(叔母さん)に財産を遺したい!」と願う方にとって、遺言書を作成しておくという事前の準備が、非常に大切になってくるのです 。
- 【重要】叔父・叔母へ財産を遺すための対策
原則として法定相続人になれない叔父や叔母が、例外的に財産を受け取れるケースが存在します。
- 遺言による遺贈(いぞう) 最も一般的なのは、被相続人が生前に有効な遺言書を作成し、その中で叔父や叔母に財産を遺贈する旨を指定していた場合です。特に、身寄りが叔父や叔母しかいない方にとって、この遺言による遺贈は、ご自身の財産を意図した相手に確実に引き継がせるための、最も重要かつ確実な手段となります。遺言書は法定相続のルールに優先するため、これを作成することで、財産が国庫に帰属することを防ぎ、お世話になった叔父・叔母へ確実に財産を遺すことが可能になります。
- 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への財産分与 法定相続人が一人もいない場合に適用される可能性がある制度です。被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者などが家庭裁判所に申し立て、認められれば財産の一部または全部を受け取れる場合があります。叔父や叔母も、献身的な介護などの事情があれば認められる可能性はありますが、あくまで例外的な救済措置であり、家庭裁判所の判断が必要となるため、遺言による遺贈ほど確実な方法ではありません。
- まとめ:意思を反映させるために専門家への相談を
結論として、甥や姪は「代襲相続」により相続人となる可能性がある一方で、叔父や叔母は法定相続人の範囲に含まれないため、原則として相続できません。
このルールは、特に法定相続人がおらず、ご自身の財産を叔父や叔母など特定の方に遺したいとお考えの場合に極めて重要となります。そのような状況で遺言書がなければ、どれだけ生前の関係が親密であっても、財産は法律の規定通りに扱われ、最終的には国庫に帰属してしまう可能性があるのです。
ご自身の意思を確実に反映させるためには、遺言書の作成が不可欠です。
これを機に、ご自身の財産を誰にどのように遺したいか、一度じっくりと考えてみてはいかがでしょうか。ご不明な点があれば、専門家への相談もご検討ください。
司法書士 半澤