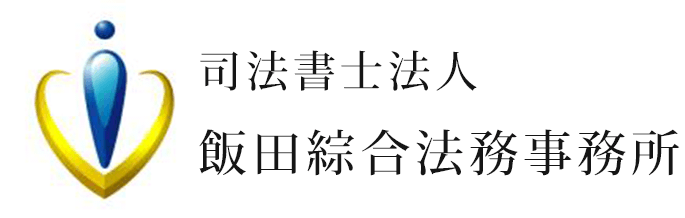相続手続きや不動産登記、さまざまな行政手続きに欠かせない戸籍謄本。これまでは本籍地のある市区町村の役所でしか取得できず、「本籍地が遠方で取得に手間がかかる」「複数の役所に請求手続きをするのが大変」といったお悩みが多く聞かれました。
そのような不便を解消するため、2024年(令和6年)3月1日から、戸籍法の一部改正により戸籍証明書等の「広域交付」制度がスタートしました。
この新しい制度によって、皆様の戸籍集めの負担が大幅に軽減されます。特に、多くの戸籍謄本を必要とする相続手続きなどでは、大変便利な制度です。
当事務所でも、この新制度を活用し、よりスピーディーな相続手続きのサポートをご提供しております。本記事では、この「戸籍の広域交付」について、ポイントを分かりやすく解説します。
「戸籍の広域交付」とは?2つの大きなメリット
戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになった制度です。この制度には、主に2つの大きなメリットがあります。
1. 【どこでも】最寄りの窓口で取得可能に
これまで、戸籍謄本は本籍地のある市区町村の役所でしか取得できませんでした 3。しかし、広域交付制度の開始により、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、他の市区町村が管理する戸籍証明書を請求できるようになりました。これにより、遠方に本籍地がある方でも、わざわざ郵送で請求したり、現地へ赴いたりする必要がなくなります。
2. 【まとめて】1か所の窓口でまとめて請求可能に
相続手続きなどでは、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)や、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。これらの方々の本籍地が全国各地に点在している場合、従来はそれぞれの市区町村に個別に請求する必要がありました。
広域交付制度では、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。これにより、手続きにかかる時間と手間を大幅に削減することが可能です。
広域交付で請求できる証明書と請求できる方
便利な広域交付制度ですが、請求できる証明書や請求できる人には一定の範囲があります。
請求できる証明書
● 戸籍証明書
● 除籍証明書
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
※戸籍抄本(個人事項証明書)や一部事項証明書は請求できません。
請求できる方
広域交付を利用して戸籍証明書等を請求できるのは、以下の範囲の方に限られます。
● 本人
● 配偶者(夫または妻)
● 父母、祖父母など(直系尊属)
● 子、孫など(直系卑属)
重要な点として、兄弟姉妹の戸籍証明書は広域交付では請求できません。また、司法書士などの代理人による請求や、郵送による請求も認められていませんのでご注意ください。
広域交付の請求方法と注意点
広域交付を利用する際は、以下の点にご留意ください。
- 請求できる方が直接窓口へ行く必要があります。
- 窓口で請求する方の本人確認が厳格に行われます。
- 顔写真付きの身分証明書の提示が必須です。
必要な持ち物
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
など、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書。
健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では請求できませんので、必ず上記のいずれかをご持参ください。
まとめ:相続手続きは司法書士にお任せください
戸籍の広域交付制度は、国民の利便性を大きく向上させる画期的な改正です。特に、2024年4月1日から義務化された相続登記の手続きにおいては、戸籍収集の負担が軽減され、よりスムーズな手続きが期待できます。
しかし、ご自身で戸籍を収集する際には、どの範囲の戸籍が必要かを正確に判断する必要があり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
私たち司法書士は、相続手続きの専門家です。相続人の調査(戸籍収集)から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。