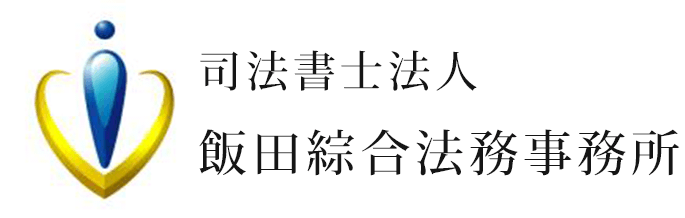「相続」や「遺言」は、多くの方にとって人生の重要なテーマです。特にご自身の想いを次の世代に確実に伝える「遺言書」の作成は、円満な相続のために非常に有効な手段です。
さて、この遺言制度が、デジタル社会の進展に合わせて大きく変わるかもしれない、ということをご存じでしょうか。現在、法務省の「法制審議会」において、遺言の新しいあり方について活発な議論が進められています 。去る2025年6月3日にも、その具体的な内容を検討する会議が開催されました 。
この議論は、弁護士、大学教授、私たち司法書士のような実務家、さらには公証人や金融機関、各種団体の代表者など、多くの専門家を交えて行われており 、今後の私たちの生活に直結する重要なものです。
本日は、この審議会で検討されている「遺言制度の見直し」のポイントを、皆様に分かりやすく解説いたします。
ポイント1:ついに登場?「デジタル遺言」の創設
今回の見直しで最も注目されているのが、パソコンやスマートフォン等で作成する「デジタル遺言」の導入です 。手書きが原則の自筆証書遺言と比べ、作成の負担が大幅に軽減される可能性があります。
審議会では、主に以下のような複数の案が検討されています。
- 【甲案】公的機関に保管しない方式
- 証人2名以上の立会いのもと、遺言の内容を口述し、その様子を録音・録画することで作成する方法などが議論されています 。
- 【乙案】公的機関が電子データを保管する方式
- 作成した遺言の電子データを、法務局などの公的機関にオンラインで申請し、保管してもらう方式です 。マイナンバーカードによる本人確認などが想定されています 。
- 【丙案】公的機関が印刷した書面を保管する方式
- パソコン等で作成した遺言書を印刷して署名し、それを法務局などの公的機関に保管してもらう方式です 。
これらの方式が実現すれば、ご自宅にいながら、より手軽で確実に遺言を残せる選択肢が増えることになります。
ポイント2:自筆証書遺言の「押印」が不要になる?
皆様にとって最も身近な自筆証書遺言についても、重要な見直しが検討されています。それは、押印要件の廃止です 。
現在、自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印することが要件です 。この「押印」がなくても遺言が有効になる可能性が議論されています 。
押印が不要になれば、より手軽に作成できる一方で、ご本人の意思で作成されたことをどう担保するかが課題となり、様々な角度から慎重な検討がなされています 。
まとめ:私たち専門家の役割
今回ご紹介した内容は、まだ「たたき台」の段階であり、法律として成立したものではありません 。しかし、国が社会の変化に対応し、国民がより利用しやすい遺言制度を目指している大きな流れは確かです。
制度が変われば、選択肢が増えて便利になる一方で、方式が複雑化し、「どの方法が自分に最適なのか」「要件を満たさず無効になってしまわないか」といった新たな不安も出てくるかもしれません。
私たち司法書士は、こうした法改正の動きを常に注視し、最新の情報を皆様にお届けする準備をしています。遺言書の作成、相続手続き、そして将来への備えについて、少しでもご関心やご不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。一人ひとりのご状況に合わせた最適な方法を、一緒に考えさせていただきます。
司法書士法人飯田綜合法務事務所
高田